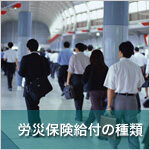遺族補償年金前払一時金
遺族補償年金の支給を受ける際に、まとまったお金が必要な場合は、遺族補償年金前払一時金として、給付基礎日額の1,000日分を上限に一時金の支給を受けることが可能です。
なお、通勤災害の場合は、遺族年金前払一時金と言います。
請求は、遺族補償年金の請求と当時に行わなければいけません。
ただし、遺族補償年金の支給決定の通知があった日の翌日から起算して1年を経過する日までの間であれば、遺族補償年金の請求後でも請求できます。
遺族補償年金前払一時金を請求できるのは、1回のみです。
したがって、既に前払一時金を請求されている場合、転給によって新たな受給権者となった者は遺族補償年金前払一時金を請求できません。
そして、55歳以上60歳未満の夫、父母、祖父母、兄弟姉妹の場合、60歳に達するまで遺族補償年金は支給されませんが、条件を満たせば遺族補償年金前払一時金は支給されるという違いがあります。
遺族補償年金前払一時金の額
給付基礎日額の200日分、400日分、600日分、800日分、1000日分のうち、受給権者が選択する額が支給されます。
遺族補償年金の支給停止
遺族補償年金前払一時金の支給を受けた場合、各月に支給されるべき年金額(前払一時金が支給されてから1年経過後の分については、年5分の単利で割り引いた額)の合計が、当該前払一時金の額に達するまで、遺族補償年金は支給停止されます。
「年5分の単利で割り引いた額」とは、前払一時金が支給されて1年経過後からの分は、元本に5パーセントの利子が必要ということです。
実際には、お金の貸し借りではないので利子を直接徴収することはできず、そこで、本来支給されるべき額からその利子分を差し引いて、その合計額がすでに受け取った遺族補償年金前払一時金の額を超えるまで支給停止という措置が取られています。
これは、前払一時金の支給を受けた者が失権して、転給により新たな受給権者になっても引き継がれる支給停止事項です。
なお、遺族補償年金前払一時金が支給されたことにより遺族補償年金が支給停止されている場合は、次の給付は行われません。
- 20歳前の傷病による障害基礎年金
- 旧国民年金法の規定による老齢福祉年金等
- 児童扶養手当等